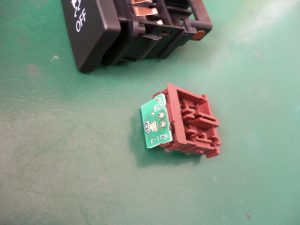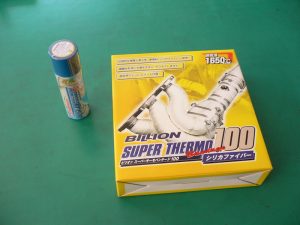ワークスにリジカラを取り付けします、写真上側の8個の方がフロント側のサブフレームに取り付ける物で、下側の2個の大きめ方がリヤのトレーリングアームの支点部分に取り付ける物になります。
リジカラとは、真鍮っぽい材質で鍔のついた大きめのワッシャーみたいな製品で、余裕を持って大きめに空けられた穴のサブフレーム固定ボルトやアームの支点部分のボルトに取り付けて芯を出すための物らしいです。


まずはフロント側にリジカラを取り付ける為にジャッキアップしてウマを掛けてタイヤを外します、作業スペースを確保する為に少し高めに上げてます。
次に車体下に潜って、赤丸で囲ったボルト部分のボディとサブフレームの間、サブフレームとボルトの間に取り付けます。


サブフレームを固定しているボルトを抜き取って付属のスレッドコンパウンドみたいなグリスをボルトとリジカラに塗って取り付けていきます。
フレームとサブフレームの隙間が狭くて取り付けがかなり大変でした。


次にロアアームを固定している部分のボルトですけど、こちらも同様にリジカラを挟み込みます、ここも隙間が狭くてかなり大変でした。

逆側にも取り付けて、トルクレンチを使ってリジカラを取り付けたM12のボルトは110Nで締め付ければフロント側が完了です。


リヤ側もジャッキアップしてタイヤを外した後、赤丸部分のボルトを取り外してリジカラを取り付けます、リヤ側の取り付け場所はこのアームの支点になってる一カ所だけです。


このワークスはタイヤハウジング内にノックスドールを塗ってあるのでボルト周りをブレーキクリーナーで拭き取ってノックスドールを剥がします。
フロント側と同様に取り外したボルトとリジカラの必要部分に付属のグリスを塗って取り付けします。


トレーリングアームを動かしながらボルトを取り付けてフロント側と同様にトルクレンチ使って110Nで締め付けます。
最後にノックスドールを剥がした部分に再度ノックスドールを塗布して作業完了です、これはかなり大変な作業でした。
この後、トー角を調整して運転してしてみたのですが、リヤ側の動きが若干スムーズになったように感じました、フロント側に対しては何の変化も感じ取る事は出来なかったですね。
フロント側に関しては、サブフレームとの固定が元々上手く仕上がってればリジカラなんて必要無い物ですし経年劣化的なズレが生じないってだけかもしれないですね。